水中毒の症状とは?1日何リットルが飲み過ぎ・依存のライン?原因や対処法も解説

ダイエット中や熱中症対策として、大量の水分を摂る方もいるでしょう。
しかし、水分を摂り過ぎると血液中のナトリウム濃度が下がり、吐き気や頭痛など水中毒の症状が現れる場合があります。
水は人間の体に必要不可欠ですが、過剰摂取は体に悪影響を及ぼすため注意が必要です。
本記事では、水の飲み過ぎで起こる水中毒の危険性や原因、対処法を詳しく解説します。
1日に必要な水分量や、ミネラルバランスを整える効果が期待できるナチュラルミネラルウォーターも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
【注意】水中毒とは?原因と主な症状

水中毒とは、水の過剰摂取により、体内のミネラルバランスが乱れる状態です。
水中毒は、低ナトリウム血症に陥りやすく、体にさまざまな症状を引き起こすうえ、最悪の場合は命の危険を伴う可能性もあります。
ここでは、水中毒の原因と主な症状を詳しく解説します。
水中毒の症状 (初期・中期・重度)
水中毒は、水の過剰摂取により体内のナトリウム濃度が異常に低下する「低ナトリウム血症」が原因で起こります。
主な症状は、ナトリウム濃度の低下度合いにより、段階的に進行します。
比較的軽度で、ほかの体調不良と間違えやすい症状の場合が多いです。
- めまい、ふらつき
- 頭痛
- 吐き気
- 多尿(トイレに行く回数が増える)
- 軽いむくみ(手足や顔など)
- だるさ、軽い疲労感
初期では、症状がわかりにくいことも少なくありません。
ナトリウム濃度の低下が進み、よりわかりやすい症状が現れます。
- 嘔吐
- 錯乱、見当識障害(時間や場所が分からないなど)
- 筋力低下、筋肉のこむら返り
- 強い倦怠感
- 食欲不振
- 注意力の低下、ぼんやりする
神経系の症状が現れはじめるのは、中期の段階です。
命に関わる危険な状態です。
脳細胞のむくみが進行し、中枢神経系に深刻な影響が出ます。
- 意識障害(呼びかけへの反応が鈍くなる、意識がなくなるなど)
- けいれん
- 呼吸困難
- 異常な発汗
- 血圧の変動
- 脳浮腫(脳の腫れ)
重度に至ると、迅速な医療処置が必要であり、永続的な脳損傷や死に至る可能性もあります。
初期の段階で症状に気づき、水分摂取量を見直したり専門家に相談したりすることが、水中毒の重症化を防ぐために重要です。

水中毒の原因
水中毒の主な原因は、血中のナトリウム濃度の急激な減少によるものです。
ナトリウムは体に必須のミネラル(電解質)の一種で、主に食塩として摂取されています。
血液中のナトリウム濃度は体内の水分量とともに腎臓で調節されており、必要な分は再吸収され、余分なものは尿として排出される仕組みです。
しかし、水を過剰に摂取すると腎臓の機能が低下し、血液中のナトリウム濃度が低下する「低ナトリウム血症」を引き起こす場合があります。
水を飲み過ぎることで低ナトリウム血症を起こした状態が、いわゆる「水中毒」です。
1日の水分摂取量は?何リットルからが飲み過ぎ・依存のライン?

飲み過ぎや依存にならないよう、1日の適切な水分摂取量を正しく理解することが、水中毒を防げます。
ここからは、1日の適切な水分摂取量や飲むタイミングを解説します。
1日の適切な水分摂取量
1日の水分摂取量は、成人の場合1.2Lが推奨され、2Lを大幅に超える摂取は飲み過ぎである可能性が高いです。
成人では、1日に約2.5Lの水が尿や便、呼吸、汗などで排出されます。
体内から減少した分の水分を補うために、2.5Lの水を摂る必要がありますが、体内で生成される0.3Lのほか、食事から1.0Lが摂取できます。
そのため、飲み物から摂取する必要量は、約1.2Lです。
1日に必要な水分量である2.5Lを超える水分摂取は、飲み過ぎといえるため、水中毒に陥るリスクが高まるでしょう。

水分摂取のベストなタイミング
水分摂取のベストなタイミングは、「喉が渇く前にこまめに摂る」ことです。
喉の渇きを感じたときには、すでに体は水分不足になりはじめています。
とくに意識したいタイミングは、次のとおりです。
- 起床時
- 入浴前後
- 運動中~後
- 就寝前
一度に大量に飲まず、コップ1杯程度(200ml前後)の量を複数回に分けて飲むことがポイントです。
適度なタイミングで飲むことで、体が効率よく水分を吸収でき、水中毒のリスクも減らせます。

【セルフチェック】水中毒の診断テスト

ここからは、水中毒の可能性を示唆するサインを確認するためのチェック項目を紹介します。
ただし、あくまでセルフチェックであり、医学的な診断ではない点に注意が必要です。
診断テスト
水中毒の可能性を示唆するセルフチェック項目は、次のとおりです。
- 喉の渇きを感じていないのに、習慣的に大量の水を飲んでしまう
- 1日に3リットル、あるいはそれ以上の水分を日常的に摂取している
- 短時間のうちに(例:1時間に1リットル以上)大量の水分を摂取することがある
- 水を飲まないと落ち着かず、不安を感じる
- 水分を飲むことへの強いこだわりや強迫観念がある
- 水分を過剰に摂取したあと、体調不良を感じることがある
チェック項目に多く当てはまる場合や、体調不良が頻繁に起こる場合は、水中毒や水を大量に飲んでいる状態である多飲症の可能性があります。
もしチェックに当てはまったら?
セルフチェックは、あくまで水中毒や多飲症の可能性に気づくための一つの目安です。
項目に当てはまる場合でも、必ずしも診断が確定するわけではありません。
しかし、いくつかのサインが見られた際は、自身の水分摂取習慣や体の状態を見直す大切なきっかけです。
チェック項目に気になる点が多かったり、体の不調を感じたりする場合は、自己判断せず、必ず専門の医療機関に相談しましょう。
内科やかかりつけ医、精神科や心療内科が適切な相談先といえます。
医師に、チェックの結果や普段の水分摂取量、具体的な症状などを詳しく伝えることで、適切な診断とアドバイスを得ましょう。
水中毒の予防法

水中毒を防ぐためには、水分摂取量や排尿回数の把握が重要です。
また、喉が渇いたと感じる前に適量摂取する、こまめな水分補給も推奨されます。
ここからは、水中毒の予防法につながる水分摂取の方法を紹介します。
1日の水分摂取量を把握しておく
水中毒を防ぐためには、1日の水分摂取量を把握しましょう。
1日に必要な水分摂取量は、約1.2Lとされていますが、運動量や体質などにより個人差があります。
とくに、運動量が多い方や汗をかきやすい方は、水分を意識的に摂ることがもとめられますが、必要以上に飲みすぎないように、飲んだ量を把握するとよいでしょう。
飲む量の把握は、水分摂取の回数やタイミングを記録する方法がおすすめです。
1日の排尿回数を把握しておく
1日の排尿回数を把握すると、体内で失われた水分量が明確になり、水中毒の予防に役立ちます。
健康な成人の排尿回数は、1日に5〜7回程度が一般的です。
排尿の回数が極端に多い場合は、水分を摂りすぎている可能性がありますが、一方で、排尿の回数が少なすぎる場合は、脱水も考えられます。
さらに、排尿の回数のみならず、尿の色にも注目すると、水分に過不足がないかも確認できます。
排尿の状態を日々確認する習慣をつけ、自身に適した水分量を調整しましょう。
毎日同じ時間に体重を測る
毎日同じ時間に体重を測ることも、水分摂取量の目安を知る手がかりです。
とくに急激な体重増加があった場合は、水分を過剰に摂取している可能性が考えられます。
たとえば、1日のうち2〜3kgの体重が増加した場合は、脂肪ではなく水分の影響であることが多いです。
また、朝と夜の体重差が極端に大きい場合も注意が必要です。
体内の水分バランスが崩れると、むくみや体調不良を引き起こす原因にもなるため、体重を毎日記録し、適量の水分補給ができているのかを確認するとよいでしょう。
水分はこまめに摂取する
水中毒を防ぐためには、一度に大量の水を飲まず、こまめに摂取しましょう。
1回の水分補給で体内に吸収される水分量は、一般的に200~250mlです。
1日の必要量を一度に飲んでも吸収されないため、喉が渇いたと感じる前に適量の摂取を心掛けましょう。
飲むタイミングは、起床時や食事の前後、汗をかきやすい運動や入浴の前後、就寝前がおすすめです。
1回コップ1杯(約200ml)程度を目安に、こまめに飲む習慣をつけましょう。
水中毒の症状が出た時の対処法 ・治し方のヒント

水中毒は体内のナトリウム濃度が急激に低下した状態であり、深刻な健康被害をもたらす可能性があります。
ここでは、水中毒であると思われる症状が現れたときの対処法について解説します。
正しい知識と対処法を知り、水中毒のリスクを減らしましょう。
水を飲むのをやめる
水中毒の症状が見られた場合には、水の摂取を制限してください。
腎機能が正常な場合、水の摂取を制限すれば血液中のナトリウム濃度が改善します。
そのため、頭痛などの症状も時間とともに軽減するでしょう。
ナトリウムを補給する
ミネラルを含む経口補水液(スポーツドリンク)や、塩分を含む食品(飴や梅干しなど)を摂取するのも効果的な方法です。
ただし、急激な補給は脳に異常をきたす恐れがあるため、少しずつ摂取するようにしましょう。
意識障害がある場合はすぐに病院を受診する
意識障害を引き起こした場合は、すぐに病院を受診してください。
治療が遅れると脳や心臓などの主要な臓器が障害され、場合により命に関わることもあります。
状況により救急車を要請し、早期に適切な治療を受けることが大切です。
イオンバランスを保ち水中毒の対策をしよう!

水中毒を予防するためには、水を飲み過ぎないことはもちろん、体内のイオンバランスを整えることも大切です。
ここでは、イオンバランスを保つために必要な成分や、その関係性について解説します。
イオンバランスとは
イオンバランスとは、体内のイオン(電解質)、つまりミネラルのバランスです。
体内のイオン(ミネラル)バランスが適切に保たれていると、体の調子が整います。
一方、イオンバランスが乱れると、体に影響を及ぼす可能性が高まります。
水中毒は、一度に大量の水を飲むことで、血液中のナトリウム濃度が急激に低下して起こる症状です。
イオンバランスの乱れにより起こる症状であるともいえるため、水中毒を防ぐためには水のみでなく、ミネラルも十分に摂取する必要があります。
イオンバランスに必要な成分の関係性
イオンバランスを保つためには、体に必要なミネラルの関係性を知ることが大切です。 ミネラルは人体に必要な栄養素の一つです。
カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などがミネラルに該当し、主に体の調子を整えるのに役立ちます。
カリウムは、ナトリウムとともに細胞内外のイオンバランスを調整し、神経や筋肉の正常な機能を支えています。
カルシウムやマグネシウムは骨や歯の形成に重要な役割を果たすミネラルです。
イオンバランスを正常に保つには、これらのミネラルの適切な摂取が欠かせません。
バランスの取れた食事と適切な水分補給が大切です。
水中毒・水全般に関するよくある質問

これまで水中毒について詳しく説明しましたが、まだ心配な方がいるかもしれません。
ここでは、水中毒に関するよくある質問をピックアップして紹介します。
水を飲む量が不安な方や病院での治療を検討している方はぜひ参考にしてください。
水は1日2リットル飲んだ方がいいのですか?
「1日2リットル」は健康維持のための水分摂取量の目安としてよく言われますが、全ての人に当てはまるわけではありません。
必要な水分量は、年齢、性別、体重、活動量、気候(季節や湿度)、健康状態などによって個人差が大きいです。また、私たちは食事からも1日に約1リットル程度の水分を摂取しています。
そのため、飲み水だけで2リットルに厳密にこだわる必要はありません。喉の渇きを感じる前にこまめに飲むこと、尿の色(濃い黄色なら不足気味、薄い黄色なら適切)などを参考に、ご自身の体調や生活に合わせて調整することが大切です。

水を飲むことはなぜダイエットにいいのですか?
水は体内の代謝を円滑にし、エネルギー消費を助けます。食前に飲むと胃が満たされ食べ過ぎを防ぎやすく、空腹感を紛らわす効果もあります。また、老廃物の排出を促し、体の巡りをよくします。
水自体はカロリーゼロなので、糖分の多い飲み物を水に置き換えることで摂取カロリーを大幅に削減できます。運動時の水分補給はパフォーマンスを維持し、より効果的な運動にも繋がります。
これらが、水がダイエットをサポートすると言われる理由です。

水以外の飲み物でも多飲すると水中毒になる場合がある?
水以外の飲み物でも、短時間に大量摂取すると水中毒を引き起こす恐れがあると考えられます。
お茶やコーヒー、ジュースも水分です。
大量摂取すると体内のイオンバランスが崩れる可能性があります。
汗を大量にかいた場合にお茶やジュースを一気に飲むと、水中毒のリスクが高まるため注意が必要です。
水分補給しても異常に喉が渇く原因は?
水分補給をおこなっても喉が渇くのは、体内の水分が足りていないことが原因です。
塩分を摂り過ぎた際に、体内のナトリウム濃度が上昇することにより喉が渇くこともあります。
塩辛い料理を食べたあとに喉が渇くのは、体内のナトリウム濃度を薄めるための働きであるとされています。
喉が異常に渇くときには、数回に分けてゆっくり水分補給するように心がけましょう。
水中毒は何日くらいで治りますか?
水中毒の回復期間は症状の重さにより異なりますが、数時間から数日程度で改善するといわれています。
軽度の場合、水分摂取を適切に調整し、ナトリウム濃度を回復させることで、数時間〜1日程度で改善することが多いです。
しかし、低ナトリウム血症を伴う重度の水中毒では、意識障害やけいれんが起こることがあり、入院治療が必要になることも考えられます。
病院で適切な治療を受けた場合でも、回復には数日〜1週間程度かかるとされています。
ナトリウム濃度の回復を急ぎすぎると、脳にダメージを与えるリスクがあるため、慎重な治療が必要です。
軽症であれば水分量の調整で回復が見込めるものの、重症の場合は必ず医療機関で治療をおこないましょう。
水中毒と精神疾患に関係はありますか?
水中毒は、精神疾患と関係がある場合もあります。
とくに、統合失調症の一部の患者には、水を過剰に飲む「心因性多飲症(精神性多飲症)」を併発する方もいます。
心因性多飲症は、ストレスや強迫観念、不安などが影響し、過剰な水分摂取をする状態です。
また、神経性やせ症や過食症といった摂食障害の患者にも、体重を減らす目的で大量の水を飲む方がいます。
過剰な水分摂取が続くと、体内のミネラルバランスが乱れ、低ナトリウム血症により水中毒を引き起こすでしょう。
精神疾患が関与している場合、水分管理と並行して、根本的な精神的サポートが必要です。
水の致死量はどのくらいですか?
水の致死量は、体重や健康状態により異なります。
ただし、健康な成人の場合、1時間に1L以上、1日3~4L以上の水を摂取すると水中毒に陥りやすく、1日6L以上は命の危険があるとされています。
水中毒は、血液中のナトリウム濃度が急激に低下している状態であるため、最悪の場合、意識障害やけいれん、呼吸困難を伴い、命を落としかねません。
水中毒を防ぐために、1.5~2Lの水をこまめに摂取するよう心がけましょう。
病院で治療する場合は何科を受診すればよいですか?
水中毒の症状が疑われる場合、内科を受診するとよいでしょう。
水中毒の症状であるめまいや頭痛、吐き気、意識障害などの症状が出ている場合は、早急に医療機関を受診してください。
病院では、主に血液検査でナトリウム濃度を測定し、低ナトリウム血症が確認された場合には、点滴がおこなわれることが多いです。
また、心因性多飲症や摂食障害など精神的な要因が関与している場合は、精神科や心療内科の受診も必要です。
摂食障害を背景に過剰な水分摂取がある場合は、栄養指導を含めた専門的なアプローチが求められます。
水をたくさん飲むと身体にどのような効果がありますか?
適度な水分補給は体に多くの良い効果をもたらします。
体内の循環が促進され新陳代謝が活発になることで、老廃物の排出(デトックス)を助けます。
また、血流が改善し、栄養素が隅々まで運ばれやすくなります。腸の動きも活発になり、便秘の予防・改善にも繋がります。肌の乾燥を防ぎ、潤いを保つ美容効果も期待できるでしょう。
ただし、一度に大量に飲むのではなく、こまめに摂取することが大切です。
水太りを見分ける方法は?解消するにはどうすればいいですか?
水太りの見分け方は、夕方の足のむくみ(靴下の跡が残るなど)、顔や手足の腫れぼったさ、指で押すと跡が残るなどが目安です。短期間での体重変動もサインの一つです。
解消するには、塩分を控えカリウム(海藻類、ナッツ類など)を多く含む食事を心がけましょう。
ウォーキングなどの適度な運動で血行を促進し、体を冷やさないことも重要です。こまめな水分補給も大切ですが、冷たい飲み物は避けましょう。長時間の同じ姿勢を避け、入浴で体を温めるのも効果的です。

まとめ
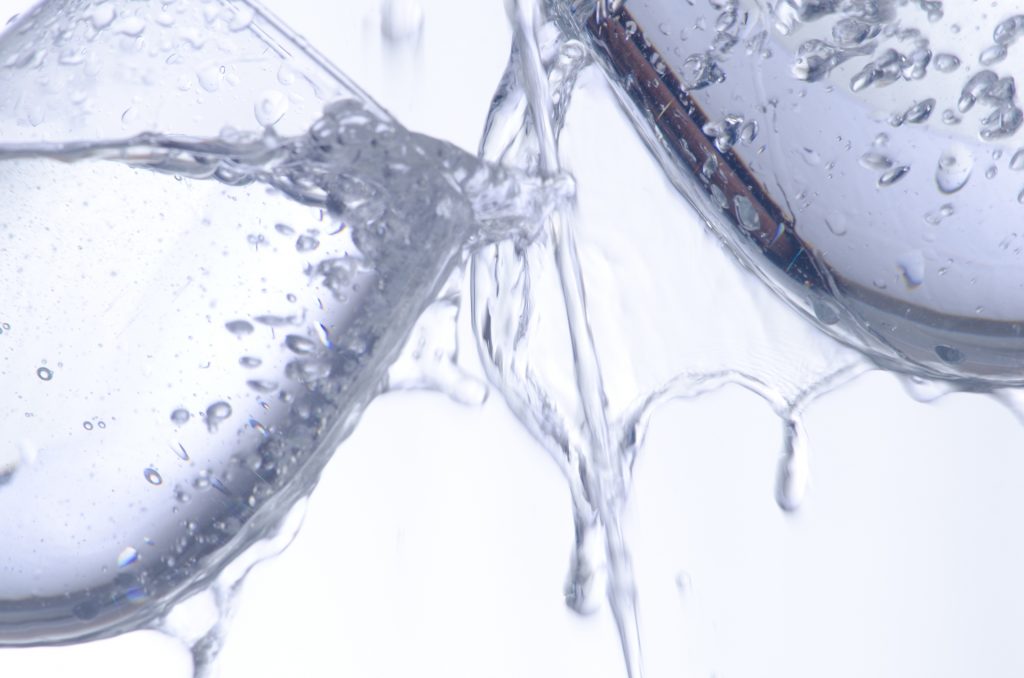
水は人間に必要不可欠なものですが、摂り過ぎると体に影響を及ぼす可能性があります。
水中毒を防ぐためには、短時間に大量の水を飲むことは避け、ミネラル豊富なナチュラルミネラルウォーターを飲むことがおすすめです。
本記事で紹介したのむシリカは、健康維持に必要なシリカをはじめとするミネラルを摂取できます。
バランスよくミネラルを摂取したい方には、普段の飲料水にのむシリカを取り入れてみてください。
<参考文献>
国土交通省|上下水道「健康のため水を飲もう」推進運動
※商品の情報は公式サイトを参考にしています。


